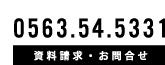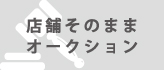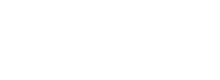ブラミツイワ02-放課後等デイサービス01
ブラミツイワ第一回社務所編が好評だったらしく、引き続きブラつくことになりました。
どーも。ミツイワ建設の放浪ライターです。
今日も、ブラついてます。
さて、第二回に白羽の矢がたったのは「放課後等デイサービス」施設の竣工までの過程をブラつきます。
皆さんは「放課後等デイサービス」ってご存知ですか?
放課後等デイサービスは2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉サービスで、就学児の通所支援サービスとして、6歳から18歳までの就学年齢のお子さんが通うことができる施設です。
ただ、どんなお子さんでも通える学童のようなものではなく、障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんのための福祉サービスで「障害児の学童」と表現されることもあります。
自立支援と日常生活の充実のための活動、創作活動、地域交流の機会の提供、余暇の提供を目的とした施設で、お子様の発達・発育の支援につながるようなサポートを行います。
今回は、西尾市に複数の施設(校舎)を持つ放課後等デイサービスさんが、施設を一箇所に集約してよりきめ細かく、より総合的な支援を行える施設を作るためにミツイワ建設にご依頼をいただきました。
しっかりした、施設を作るためにまずは「基礎」から作り上げていきます!!

前回の社務所編でも触れましたが、基礎工事は地味でよくわからない。という方も多いのではないでしょうか?
しかし、基礎工事は『家づくりの土台となるとても重要な部分』です。
基礎工事とは、文字通り地面と建物のつなぎ部分にあたる”基礎”を造るための工事のことであり、地盤と建物をつなぐ重要なパイプ役と位置付けられます。
建物の重さ、地震の揺れなどから建物が沈んでしまう。傾いてしまう。といった不同沈下を防ぐ大切な工事です。
今回は社務所編(その2)でお目見えしなかった「配筋」パターンをご紹介。

鉄格子が地面いっぱいに配置されています。
これが「配筋」。
背中の筋肉ではありません。
配筋は基礎の寿命や強度に直接影響がある非常に重要な工程で、建築基準法などでも様々なルールが決められています。
ピッチを確認したり、継ぎ手の定着確認したりと、基礎のコンクリートを打設すると完全に隠れてしまう部分なので、しっかりと確認を行います。
問題がなければ、基礎コンクリートを流していきます。

さて、コンクリートを流すだけではなく「打設」と言いますが、皆さんはなぜ「打設」と言うかご存知ですか?
基礎工事はただ生コンクリートを満遍なく流すのではなく、高密度に充填するため、入念に突いたり叩いたりして、空気や水を追い出すことが必要です。
そのため「打ち込み」と表現する、大工さんもいます。
基礎がしっかりと固まったら、今度は基礎内部の立ち上がり型枠組みです。

鋼と木、どちらかが用いられますが、今回は鋼ですね!
立ち上がりは、建物完成後の点検を可能とする為、多湿による白アリ被害を避けるために住宅建築には欠かせない工程です! 縁の下ですね!
どこまで流し込むのか? という目標のレベルポインターや基礎と基礎の上に敷く土台を緊結するための補強金物としてアンカーボルトを設置して、コンクリートを型枠の中に再度流し込んでいきます。


しっかりと乾いて、型枠を外すとこんな感じ。
土台となる木もしっかりと接合され、これで上物を建てる準備が完了です!
次回は、いよいよ建物本体に突入です!
鉄筋・鉄骨造だった社務所とは異なり、木造建築となりますので、その違いもお見せできればと思います!
つづく